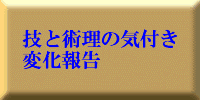 |
'01 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 '00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 '99 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2000年8月4日(金)
都内であった稽古会で、先日来の一連の気づきを試みる。柾目返、小手返、杢目返、浪之上、切込入身等の技にいままでにない手応えがあった。
それらの技に共通することは、技をかける時に決して大きく崩そうとせず、強大な相手がどう頑張っても子供にでも動かされてしまう、いわばアソビ分の数㎝の距離程度を動かすつもりで技を行なうということである。
もちろん、そのアソビ分の数㎝をただ動かしたところで何も変化は起らない。そこを技とするためには、その数㎝手を動かす時に全身の動きをそこに介入させるのである。そして、その全身の動きの介入は、主として僅かな膝の抜きを中心に行なうのである。
実際には、相手との状態によりかなり沈んでいる場合もあるが、私自身の感覚では5㎜程度膝を抜いて沈んでいるという感じである。
このような動きの技を受けた人達に感想を聞くと、掴んでいた場合など掌の中で突然何かがはじけるような感じがしたりするらしい。そのため人によっては指を痛めそうで、再度掴むことにためらいが出るとのことだった。
とにかく、現在のこの私の動きは柔らかいフワッとした動きではないので、評判は必ずしもよくない。もっともいままでも剛柔の動きが交互に現れて技が変化してきたのだから、また柔らかくなることもあるとは思うが……。
都内であった稽古会で、先日来の一連の気づきを試みる。柾目返、小手返、杢目返、浪之上、切込入身等の技にいままでにない手応えがあった。
それらの技に共通することは、技をかける時に決して大きく崩そうとせず、強大な相手がどう頑張っても子供にでも動かされてしまう、いわばアソビ分の数㎝の距離程度を動かすつもりで技を行なうということである。
もちろん、そのアソビ分の数㎝をただ動かしたところで何も変化は起らない。そこを技とするためには、その数㎝手を動かす時に全身の動きをそこに介入させるのである。そして、その全身の動きの介入は、主として僅かな膝の抜きを中心に行なうのである。
実際には、相手との状態によりかなり沈んでいる場合もあるが、私自身の感覚では5㎜程度膝を抜いて沈んでいるという感じである。
このような動きの技を受けた人達に感想を聞くと、掴んでいた場合など掌の中で突然何かがはじけるような感じがしたりするらしい。そのため人によっては指を痛めそうで、再度掴むことにためらいが出るとのことだった。
とにかく、現在のこの私の動きは柔らかいフワッとした動きではないので、評判は必ずしもよくない。もっともいままでも剛柔の動きが交互に現れて技が変化してきたのだから、また柔らかくなることもあるとは思うが……。
以上1日分/掲載日 平成12年8月6日(日)
2000年8月5日(土)
このところ日々展開と気づきがある。
今日は柾目返などで相手に持たれたり払わせたりする手を、抜刀術のとき刀を抜く方の手ではなく、鯉口を握って鞘を送る側の手の働きの要素で使うと、いままでで最もスムーズに相手を崩せることを発見した。
この発見は先日来の一連の気づきのなかにある、手はほとんどアソビの範囲内、膝の抜きも極く僅か、その短い時間内に全身を働かせるという゛回転体の入れ子構造゛から一歩踏み込んだ術理の流れで生まれてきたものである。
抜刀術の体術への応用はいままでにもいくつかあったが、いままでは柄にかけた手が抜刀の体勢そのものの応用であって、鯉口を握った鞘の送りの手を使うということは初めてである。
しかし今回、現にこの使い方が有効であったので、稽古の後あらためて検討してみた。
それでわかったことは、鞘を送るという手を後方へ動かす動きは、前方へ手を出すときには消したつもりでもつい起りがちになる踏ん張り、すなわち『固定化した支点によるヒンジ運動』に展開する要素が、より消えるらしいということである。
また、抜刀術という一瞬の間に体全体を働かせるという動きにより、通常の身体感覚では気づきにくい、より有効な身体作動のルートが開発されているということもあるらしい。
後者の理由は、先日、奥志賀高原に行った折、河原の不安定な石の上で抜刀・納刀の稽古をしたのだが、その時あらためて抜刀術の身体の使い方の重要さに気づいたことが潜在的に働いていたのかもしれない。
しかし、グラグラと不安定な石の上での抜刀・納刀、特に私が根岸流の恩師・前田勇先生に教わった前田納刀(抜いていた太刀の切先をダイレクトに鯉口に入れる)は、ひとつ間違えばそのまま切腹という危険なものだけに、とても人には勧められない。
しかし、ひとつ間違えば大怪我という緊張感の許でやることは、やはりそれなりに得るものがある。
それにしても、この奥志賀のブナ、ミズナラの原生林は素晴らしかった。東北以外にも、また恋人ならぬ恋所ができてしまった。
このところ日々展開と気づきがある。
今日は柾目返などで相手に持たれたり払わせたりする手を、抜刀術のとき刀を抜く方の手ではなく、鯉口を握って鞘を送る側の手の働きの要素で使うと、いままでで最もスムーズに相手を崩せることを発見した。
この発見は先日来の一連の気づきのなかにある、手はほとんどアソビの範囲内、膝の抜きも極く僅か、その短い時間内に全身を働かせるという゛回転体の入れ子構造゛から一歩踏み込んだ術理の流れで生まれてきたものである。
抜刀術の体術への応用はいままでにもいくつかあったが、いままでは柄にかけた手が抜刀の体勢そのものの応用であって、鯉口を握った鞘の送りの手を使うということは初めてである。
しかし今回、現にこの使い方が有効であったので、稽古の後あらためて検討してみた。
それでわかったことは、鞘を送るという手を後方へ動かす動きは、前方へ手を出すときには消したつもりでもつい起りがちになる踏ん張り、すなわち『固定化した支点によるヒンジ運動』に展開する要素が、より消えるらしいということである。
また、抜刀術という一瞬の間に体全体を働かせるという動きにより、通常の身体感覚では気づきにくい、より有効な身体作動のルートが開発されているということもあるらしい。
後者の理由は、先日、奥志賀高原に行った折、河原の不安定な石の上で抜刀・納刀の稽古をしたのだが、その時あらためて抜刀術の身体の使い方の重要さに気づいたことが潜在的に働いていたのかもしれない。
しかし、グラグラと不安定な石の上での抜刀・納刀、特に私が根岸流の恩師・前田勇先生に教わった前田納刀(抜いていた太刀の切先をダイレクトに鯉口に入れる)は、ひとつ間違えばそのまま切腹という危険なものだけに、とても人には勧められない。
しかし、ひとつ間違えば大怪我という緊張感の許でやることは、やはりそれなりに得るものがある。
それにしても、この奥志賀のブナ、ミズナラの原生林は素晴らしかった。東北以外にも、また恋人ならぬ恋所ができてしまった。
以上1日分/掲載日 平成12年8月7日(月)
2000年8月10日(木)
直打法による(すなわち飛行中の剣が、手から離れてから的に届くまで4分の1回転以上させない手裏剣術の打法)打剣は、剣の回転を抑えて打つというその性質上、三間半以上、四間(7.2m)ぐらいになってくると、どうしてもその距離からくる誘いで体がうねり系の゛投げ゛になってしまいがちになる。
それを克服するため、そのずっと手前、半間か一間ほどのところにある何かを短刀のようなもので斬るつもりになって体を使ったらいいのではないかということは以前にも考えたことがあった。しかし当時その成果はあまり芳しいものではなかった。ところが今日それを試みると、剣の飛びも綺麗だし、手が粘っていても剣の抑えも十分利く。以前もこの術理を考えつきながら、現実にはたいした効果が出せなかったのは、まだ武術としての動きが今よりもずっと育っていなかったからだろう。
自分でも思いがけないほど気持ちよく通る剣を見ているうち、この距離から来る誘いに誘われない的の見方というのを体術に置き換えて考えてみると、相手に持たれたりいなされようとしていても、その接触感覚に誘われない身体の操作法という新しい局面が拓けて来るかもしれないと思った。
現在の四間離れた的面を見るとどうしても誘われるから、その手前辺りに目の焦点を合せる状況が今後どう変ってゆくかは興味深い。松林左馬之助が開いた願立ではしきりに「眼心身一致して」ということを説いていたが、その辺のことに関して何か新しい発見でもあればと期待している。
とにかく、うねった投げではなく゛斬り゛というのは、うねった投げにくらべてずっとアソビ・ユルミがない(鞭の働きにたとえられるうねり系はアソビ・ユルミがあるから、うまくうねって力が増大するわけである)。これがあると瞬時に方向転換ができないから、うねり系の動きは斬りの動きとは本質的に違うのだろう。
今後、抜刀術と打剣との間にいままで気づかなかった密接な関連について気づくこともあるかもしれず、それはちょっと楽しみである。
直打法による(すなわち飛行中の剣が、手から離れてから的に届くまで4分の1回転以上させない手裏剣術の打法)打剣は、剣の回転を抑えて打つというその性質上、三間半以上、四間(7.2m)ぐらいになってくると、どうしてもその距離からくる誘いで体がうねり系の゛投げ゛になってしまいがちになる。
それを克服するため、そのずっと手前、半間か一間ほどのところにある何かを短刀のようなもので斬るつもりになって体を使ったらいいのではないかということは以前にも考えたことがあった。しかし当時その成果はあまり芳しいものではなかった。ところが今日それを試みると、剣の飛びも綺麗だし、手が粘っていても剣の抑えも十分利く。以前もこの術理を考えつきながら、現実にはたいした効果が出せなかったのは、まだ武術としての動きが今よりもずっと育っていなかったからだろう。
自分でも思いがけないほど気持ちよく通る剣を見ているうち、この距離から来る誘いに誘われない的の見方というのを体術に置き換えて考えてみると、相手に持たれたりいなされようとしていても、その接触感覚に誘われない身体の操作法という新しい局面が拓けて来るかもしれないと思った。
現在の四間離れた的面を見るとどうしても誘われるから、その手前辺りに目の焦点を合せる状況が今後どう変ってゆくかは興味深い。松林左馬之助が開いた願立ではしきりに「眼心身一致して」ということを説いていたが、その辺のことに関して何か新しい発見でもあればと期待している。
とにかく、うねった投げではなく゛斬り゛というのは、うねった投げにくらべてずっとアソビ・ユルミがない(鞭の働きにたとえられるうねり系はアソビ・ユルミがあるから、うまくうねって力が増大するわけである)。これがあると瞬時に方向転換ができないから、うねり系の動きは斬りの動きとは本質的に違うのだろう。
今後、抜刀術と打剣との間にいままで気づかなかった密接な関連について気づくこともあるかもしれず、それはちょっと楽しみである。
以上1日分/掲載日 平成12年8月15日(火)
2000年8月17日(木)
このところ手裏剣術の稽古に集中している。一昨日は午前2時頃からはじめたところ、気づくことが次々とあって、結局明け方(15日の)までやめることが出来なかった。
打剣で的を直接見ず「手前の空間を斬るようにする」ということはすでに述べたが、その斬るという動作を行うにあたって腕全体にアソビのない、ある独特の速さがあり、それより遅くても速くても破れが出て飛行する剣に飛色(乱れ)が出ることがわかってきた。
ではどうすればより鋭い威力のある打ちが出せるかだが、これはこの腕と全身の協調に、ある種の比例関係のようなものがあるらしい。
それに関連して手之内におさめた剣の位置が1~2㎜違っても、この全身の協調にきわめて大きな影響があるようで、剣をわずかに指先の方に出すだけで感覚的にはハッキリしてくるが、同時にうねり系のピッチングの動きになりやすい。といって少し奥に入ればなんとも不自由で嫌な感じがしてくる。
そのためにも用いる剣は横手筋を切った入念に作った剣が望ましい。もちろんあり合せのものを時に応じて打つ能力も大事だが、精妙な技の育成には入念に作られた道具は欠かせない。
俗に「弘法筆を選ばず」などというが、弘法大師その人は唐から筆作りまで学んできており、時の皇太子にあてた手紙に「良工は先ずその刀を利くし、能書は必ず好筆を用う」と書いているほど道具も吟味している。
剣を手之内の、ここぞというところに置き、腕にユルミ、アソビの生じないようにし、膝の僅かなヌキでその腕の状態を保ったまま剣を飛す。そこに呼吸も関係してくるし、何重にも厳重な条件がついてくる。
稽古していて「これが型稽古の意味であり、その型とは見た目の形より、その時々の感覚に厳密になることだ」と思った。おそらくは、こうやって規矩が出来てゆくのであろう。゛型稽古゛ということの重要性が、ここ2、3日の間に、いままでにない実感を伴って認識できるようになってきた。
このところ手裏剣術の稽古に集中している。一昨日は午前2時頃からはじめたところ、気づくことが次々とあって、結局明け方(15日の)までやめることが出来なかった。
打剣で的を直接見ず「手前の空間を斬るようにする」ということはすでに述べたが、その斬るという動作を行うにあたって腕全体にアソビのない、ある独特の速さがあり、それより遅くても速くても破れが出て飛行する剣に飛色(乱れ)が出ることがわかってきた。
ではどうすればより鋭い威力のある打ちが出せるかだが、これはこの腕と全身の協調に、ある種の比例関係のようなものがあるらしい。
それに関連して手之内におさめた剣の位置が1~2㎜違っても、この全身の協調にきわめて大きな影響があるようで、剣をわずかに指先の方に出すだけで感覚的にはハッキリしてくるが、同時にうねり系のピッチングの動きになりやすい。といって少し奥に入ればなんとも不自由で嫌な感じがしてくる。
そのためにも用いる剣は横手筋を切った入念に作った剣が望ましい。もちろんあり合せのものを時に応じて打つ能力も大事だが、精妙な技の育成には入念に作られた道具は欠かせない。
俗に「弘法筆を選ばず」などというが、弘法大師その人は唐から筆作りまで学んできており、時の皇太子にあてた手紙に「良工は先ずその刀を利くし、能書は必ず好筆を用う」と書いているほど道具も吟味している。
剣を手之内の、ここぞというところに置き、腕にユルミ、アソビの生じないようにし、膝の僅かなヌキでその腕の状態を保ったまま剣を飛す。そこに呼吸も関係してくるし、何重にも厳重な条件がついてくる。
稽古していて「これが型稽古の意味であり、その型とは見た目の形より、その時々の感覚に厳密になることだ」と思った。おそらくは、こうやって規矩が出来てゆくのであろう。゛型稽古゛ということの重要性が、ここ2、3日の間に、いままでにない実感を伴って認識できるようになってきた。
以上1日分/掲載日 平成12年8月19日(土)
2000年8月24日(木)
昨夜というか、今日の夜明け前の午前2時半頃、22日におめにかかった整体協会の野口裕之先生の「つまり体は動かないっていうことですよ」というお話を思い返しながら、打剣の稽古をしようとして何気なくテレビをつけたところ、自然農法の大御所的存在である福岡正信翁のインタビュー番組をNHK教育テレビでやっていた。
福岡翁の『わら一本の革命』には20数年前、私もすくなからぬ影響を受けた一人だが、その徹底した科学不要というか有害論には、あらためて頭が下がった。急いで録画しながら、その福岡翁の説法の雰囲気のなかで稽古した。
稽古しながらあらためて、ウエイトトレーニング等は化学肥料や農薬漬の農法と同じだと感じ、術といえるほどの動きとは、その人にすでに備わっている体重や手足の働きを活用しきることではないかと思った。
そう気づいてみると打剣という手之内の小剣を飛ばす動きに於いても、ただ上に伸びる働きと釣り合いをとる体の沈みがあり、アソビ、ユルミをとると弓射と同じく「会(弓を引き絞った状態)」もあり、自然な「離れ」もあるのだということがわかってきた。
それにしても福岡翁の畑には種々な虫が飛びかいながら、野菜の葉に明確な虫に喰われた跡がないのは見事であった。それを見ながら、キャベツ畑などを無農薬にするといっぺんに青虫に喰い荒らされるというのは、人間の何事も効率よく儲けたいというさもしさを戒める自然の働きではないかという思いが浮かんだ。このところ、人間が農業を始めたということが、今日の人類の不幸の始まりではないかとの思いに沈んでいたが、このような農法であれば、自然の営みを損なうこともきわめてすくなかったに違いない。
番組中で福岡翁が、自然農法を50年やってきて、自然というものがますますわからなくなったと語られたことが何よりも印象に残った。
種子を粘土のなかにまるめ込み、それをただ蒔くだけで、後は手入れらしいことはまったくといっていいほどしないこの農法の玄妙さから、自然ということの奥の深さをあらためて教えてもらえる。この世界に触れ、自然の奥深さに眼が開かれれば、虚栄に満ちた現代社会の魔手にも、怪しげな宗教の勧誘にもまったく動じることはなくなるだろう。
現代社会の常識に媚びぬ福岡翁にあらためて深く敬意を表したい。
昨夜というか、今日の夜明け前の午前2時半頃、22日におめにかかった整体協会の野口裕之先生の「つまり体は動かないっていうことですよ」というお話を思い返しながら、打剣の稽古をしようとして何気なくテレビをつけたところ、自然農法の大御所的存在である福岡正信翁のインタビュー番組をNHK教育テレビでやっていた。
福岡翁の『わら一本の革命』には20数年前、私もすくなからぬ影響を受けた一人だが、その徹底した科学不要というか有害論には、あらためて頭が下がった。急いで録画しながら、その福岡翁の説法の雰囲気のなかで稽古した。
稽古しながらあらためて、ウエイトトレーニング等は化学肥料や農薬漬の農法と同じだと感じ、術といえるほどの動きとは、その人にすでに備わっている体重や手足の働きを活用しきることではないかと思った。
そう気づいてみると打剣という手之内の小剣を飛ばす動きに於いても、ただ上に伸びる働きと釣り合いをとる体の沈みがあり、アソビ、ユルミをとると弓射と同じく「会(弓を引き絞った状態)」もあり、自然な「離れ」もあるのだということがわかってきた。
それにしても福岡翁の畑には種々な虫が飛びかいながら、野菜の葉に明確な虫に喰われた跡がないのは見事であった。それを見ながら、キャベツ畑などを無農薬にするといっぺんに青虫に喰い荒らされるというのは、人間の何事も効率よく儲けたいというさもしさを戒める自然の働きではないかという思いが浮かんだ。このところ、人間が農業を始めたということが、今日の人類の不幸の始まりではないかとの思いに沈んでいたが、このような農法であれば、自然の営みを損なうこともきわめてすくなかったに違いない。
番組中で福岡翁が、自然農法を50年やってきて、自然というものがますますわからなくなったと語られたことが何よりも印象に残った。
種子を粘土のなかにまるめ込み、それをただ蒔くだけで、後は手入れらしいことはまったくといっていいほどしないこの農法の玄妙さから、自然ということの奥の深さをあらためて教えてもらえる。この世界に触れ、自然の奥深さに眼が開かれれば、虚栄に満ちた現代社会の魔手にも、怪しげな宗教の勧誘にもまったく動じることはなくなるだろう。
現代社会の常識に媚びぬ福岡翁にあらためて深く敬意を表したい。
以上1日分/掲載日 平成12年8月30日(水)
2000年8月31日(木)
久しぶりに信州の江崎義巳氏来館。
体術をいくつかやったが、手裏剣術の一人稽古でここまで感覚が磨けるものなのだ、とあらためて感じ入る。
その手裏剣術では、私が今年の夏初めて、手が汗で粘ってもそれに悩まされず打てるようになったのを見てもらったが、これには感嘆された。自分の技を他人に「感嘆された」などと書くのは、ちょっとどうかとは思うが、手裏剣術の難しさを知ることと、その思い入れの深さにおいては私とどちらかというほどに、この道で話の通じる江崎氏に評価されるのは、他の誰に言われるより言葉が身体にしみ入ってきて有難い。
それに江崎氏の「とても夏(手が汗で粘っている時ということ)四間打っているようにみえません」という感想が適確。また「あの動きであれほど剣が伸びるとは」と、私の打剣の動きが質的に明らかに変ってきたとの感想も聞くことができた。
しかし、「この手のベタつきでは四間なんてとても無理ですよ」と言っていた江崎氏が、1時間ぐらいのうちになんとか通るものも出てきたから、やはり目の前で「ああ出来るのだ」ということを、確認するというのは学びの原点であり最も意味のあることなのだろう。
最近は、とにかく体の動きのアソビ、ユルミをとることを心がけているが、それによって体術の技も力が鋭く先端が尖る、という感覚が出はじめ、片手両手持たせを下へ沈める゛浪之下゛や、対タックルの体当たり、相撲の四つなどにその効果が出てきている。
そして、その体術の成果を再び打剣の工夫にも役立てるという循環が、このところ出はじめている。
とにかく、20~30分でも稽古すれば必ず気づきがあるという状況。たとえば、ついこの間まで剣を飛すのに「手で斬るように」とやっていたのが、今ではそれが姑息に感じられ、体が弓の弦のようになってアソビ、ユルミなく結果としての斬りとなっているように身体を使うようになってきている。
とにかく今は進めるうちに進んでおこうと思っている。
久しぶりに信州の江崎義巳氏来館。
体術をいくつかやったが、手裏剣術の一人稽古でここまで感覚が磨けるものなのだ、とあらためて感じ入る。
その手裏剣術では、私が今年の夏初めて、手が汗で粘ってもそれに悩まされず打てるようになったのを見てもらったが、これには感嘆された。自分の技を他人に「感嘆された」などと書くのは、ちょっとどうかとは思うが、手裏剣術の難しさを知ることと、その思い入れの深さにおいては私とどちらかというほどに、この道で話の通じる江崎氏に評価されるのは、他の誰に言われるより言葉が身体にしみ入ってきて有難い。
それに江崎氏の「とても夏(手が汗で粘っている時ということ)四間打っているようにみえません」という感想が適確。また「あの動きであれほど剣が伸びるとは」と、私の打剣の動きが質的に明らかに変ってきたとの感想も聞くことができた。
しかし、「この手のベタつきでは四間なんてとても無理ですよ」と言っていた江崎氏が、1時間ぐらいのうちになんとか通るものも出てきたから、やはり目の前で「ああ出来るのだ」ということを、確認するというのは学びの原点であり最も意味のあることなのだろう。
最近は、とにかく体の動きのアソビ、ユルミをとることを心がけているが、それによって体術の技も力が鋭く先端が尖る、という感覚が出はじめ、片手両手持たせを下へ沈める゛浪之下゛や、対タックルの体当たり、相撲の四つなどにその効果が出てきている。
そして、その体術の成果を再び打剣の工夫にも役立てるという循環が、このところ出はじめている。
とにかく、20~30分でも稽古すれば必ず気づきがあるという状況。たとえば、ついこの間まで剣を飛すのに「手で斬るように」とやっていたのが、今ではそれが姑息に感じられ、体が弓の弦のようになってアソビ、ユルミなく結果としての斬りとなっているように身体を使うようになってきている。
とにかく今は進めるうちに進んでおこうと思っている。
以上1日分/掲載日 平成12年9月2日(土)